色彩検定は、色に関する幅広い知識や技能を問う検定試験です。
「色はセンスの問題だから…」
「センスがないから色使いが苦手…」
など、色はセンスの問題だと考えている人は多いのではないでしょうか。
色にはさまざまな特徴や理論、法則があり、そのルールを学ぶことができます。
色のルールを学ぶことでセンスをよくすることもできるのです。
色彩検定は、各業界からの評価が高く、受検者は学生をはじめ社会人においてもファッション、インテリア、グラフィックなどのデザイナー、販売、企画、事務といった幅広い職種に広がっています。
色の基礎から学ぶことができる色彩検定に対応したおすすめ通信講座をご紹介します。
色彩検定の通信講座
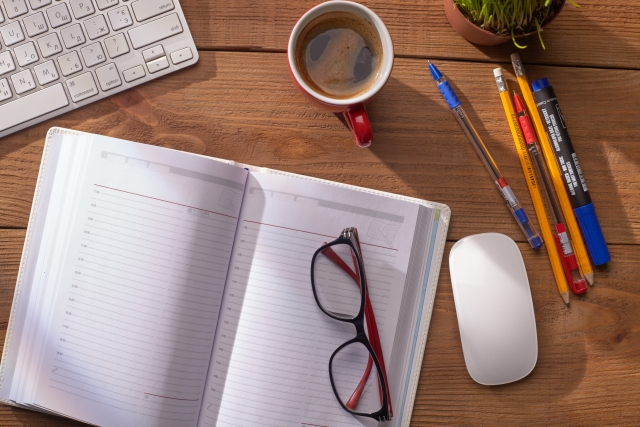
色彩検定とは
色彩検定は文部科学省後援の公的資格です。
文部科学省後援の検定試験ということから、高校、短大、大学、専門学校など、学生の受験者が多いのも特徴です。
はじめて色を学ぶ人向けの3級から、実務レベルの2級、プロフェッショナル向けの1級と一般社会人向けのUC級が設定されています。
色について基礎からしっかり学ぶこと、色を扱った仕事をしていて知識を整理すること、さらなるスキルアップを目指すことなどができます。
1級(プロフェッショナル向け)
色彩と文化、色彩調和論、測色、色彩とビジネス、ファッションビジネス、景観計画における色彩基準など。
2級と3級の内容に加え、以上のような事柄を十分に理解し、技能を持っていること。
2級(実務に応用したい人向け)
色のUD、照明、表色系、色彩調和、配色イメージ、ビジュアル、ファッション、インテリア、景観色彩など。
3級の内容に加え、以上のような基本的な事柄を理解し、技能を持っていること。
3級(初めて色を学ぶ人向け)
光と色、色の分類と三属性、色彩心理、色彩調和、配色イメージ、ファッション、インテリアなど。
以上のような色彩に関する基本的な事柄を理解していること。
UC級(一般社会人・公共、福祉、設計者など)
色が見えるしくみ、ユニバーサルデザイン、色覚の多様性、高齢者の見え方など。
配色における注意点や改善方法を理解していること。
色彩検定の通信講座
ヒューマンアカデミーの通信講座には、色彩検定試験に対応した対策講座が用意されています。
色彩について初めて学習する人でも効率的に学べて、短期間で3級・2級のダブル合格を目指せる内容になっています。
色彩検定3級・2級パックコース
- 標準学習期間:4ヵ月
- 在籍期間:4ヵ月
- 添削回数:9回
- 受講料:46,000円
- 分割払い:月々3,200円(例)
講座の特長
- 公式テキストを用いた学習
- わかりやすい映像講義
- 色彩検定3級・2級のダブル合格
教材の内容
- 色彩検定公式テキスト(3級・2級)各1冊
- 攻略ナビテキスト(3級・2級)各1冊
- オリジナル問題集(3級・2級)各1冊
- 配色カード
- 直前対策答案練習(3級・2級)各1式
3級カリキュラム
- 色のはたらき
- 光と色
- 色の表示
- 色彩心理
- 色彩調和
- 配色イメージ
- ファッション
- インテリア
2級カリキュラム
- 色のユニバーサルデザイン
- 光と色
- 色の表示(表色系)
- 色彩心理
- 色彩調和
- 配色イメージ
- ビジュアル
- ファッション
- インテリア
- 景観色彩
色彩検定講座のメリット
色の基礎から色の組み合わせ方、専門分野における利用などを幅広く学習するので、初めて学ぶ人でも色の理論を身につけることができます。
色を基礎から学びたい人や色を使った仕事をしている人、スキルアップして資格取得したい人におすすめです。
受講生の声
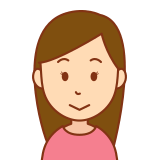
テキストと一緒に勉強の進め方や資料の使い方など詳しい案内も送付されており、勉強の進めやすくとてもありがたかったです。
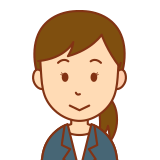
年明けに受講を始めて6月の試験を受けています。問題集が記述式だったのは良かったと思います。
(ヒューマンアカデミー「たのまな」サイトより)
色彩検定の試験内容
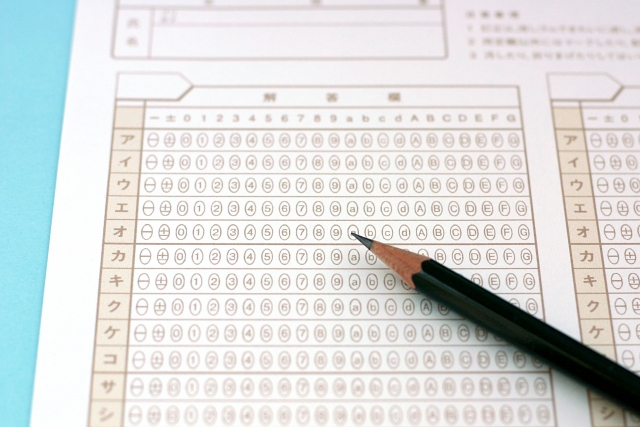
色彩検定試験の概要
色彩検定は色に関する幅広い知識や技能を問う検定試験です。
学生からプロまで幅広い層の人が受検しています。
受検資格
制限なし
試験日
- 1級:【1次】11月【2次】12月
- 2・3・UC級:6月、11月
受検地
希望エリアの公開会場で受検(公開会場は北海道から沖縄まで全国に設置)
1級
- 出題方法
【1次】マークシート方式【2次】記述方式(一部実技) - 出題範囲
色彩と文化、色彩調和論、色の知覚、ファッションビジネス、プロダクトデザイン、インテリアカラーコディネーション、環境色彩、ユニバーサルデザインなど - 合格基準
満点の70%程度
2級
- 出題方法
マークシート方式(一部記述式) - 出題範囲
照明、色名、表色系、配色技能、配色イメージ、ビジュアルデザイン、ファッション、プロダクト、インテリア、エクステリアなど - 合格基準
満点の70%程度
3級
- 出題方法
マークシート方式 - 出題範囲
光と色、色の分類と三属性、色彩心理、色彩調和、色彩効果、ファッション、インテリアなど - 合格基準
満点の70%程度
UC級
- 出題方法
マークシート方式(一部記述式) - 出題範囲
色が見えるしくみ、ユニバーサルデザイン、色覚の多様性、高齢者の見え方、色覚の多様性や高齢者の見え方に配慮した配色方法など - 合格基準
満点の70%程度
合格率
- 1級:40%程度
- 2級:70%程度
- 3級:75%程度
- UC級:85%程度
社会人受検者の業種
- 流通・販売・小売
- サービス業
- IT・コンピューター
- 各種メーカー
- ファッション・デザイン
- 住宅・建築
- 公務員・教職員
(色彩検定協会「2023年度色彩検定受検者データ」より)
色彩検定の資格勉強

色彩検定試験の対策
色彩検定の資格を取得するには、独学や資格・通信講座で勉強する方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、自分の状況やかけられる時間、費用など自分の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。
公式テキストが市販されていますので、テキストと問題集を繰り返す独学でも合格を目指すことができます。
独学に不安があったり、短期間で効率的に学習を進めたい人は、試験に対応したお手頃価格の通信講座を上手に活用することをおすすめします。
色彩検定公式テキスト2級
色彩検定公式テキスト3級
資格のダブル取得
色彩検定のレベルは、自分の知識や目的に合わせて選択し、さらに専門性を高める資格を取得することで、活躍の場を広げることができるようになります。
色彩検定と同様に色彩を専門的に学べる資格としてはカラーコーディネーターがあります。
それぞれの資格の特徴や強みを理解して、自分のキャリアに合った資格を選ぶことが大切です。
販売士
販売士(リテールマーケティング検定)は、販売のプロを認定する公的資格です。
流通・小売業界やメーカーなどで活用できます。
インテリアコーディネーター
インテリアコーディネーターは、住空間をデザインするプロフェッショナルです。
メーカーや専門店、小売店などで活用できます。
まとめ
私たちは日常生活のなかで、無意識のうちに色から大きな影響を受けています。
色彩の効果や役割を重視する企業は増加していますので、色彩について専門的に学び、身につけた知識は、さまざまな分野で幅広く活用することができるでしょう。




【参考】
・公益社団法人色彩検定協会
・東京商工会議所検定サイト
・ヒューマンアカデミー「たのまな」サイト



