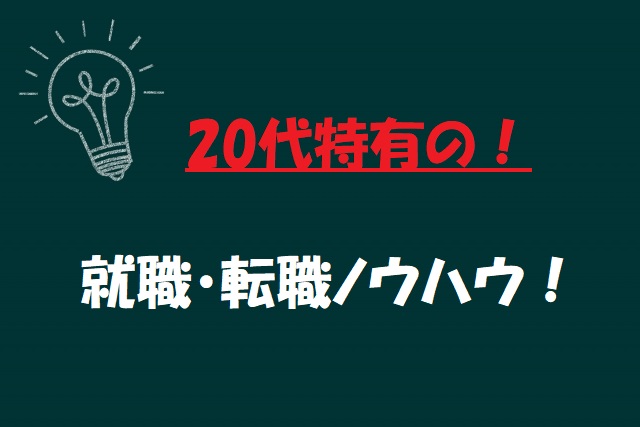キーワード解説

賃金
賃金とは、労働の対償として事業主が従業員に支払うもののことです。
労働基準法では賃金について、
「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
と定義しています。
事業主が従業員に支払うものであって、かつ労働の対価として支払われるものは、すべて賃金に該当し、現金以外のものも含まれます。
事業主が従業員に支払うものでなければ、賃金にはなりません。
例えば、客から受け取るチップのようなものは賃金には該当しません。
また結婚祝金、病気見舞金、弔慰金など任意的な給付は労働の対価ではないとされ、賃金にはなりません。
ただし、就業規則や労働協約などにあらかじめ支給基準が明記され、使用者に支払義務があるものは賃金として扱われます。
任意で支給される退職金は賃金になりませんが、退職金制度があれば、退職金は賃金になります。
現物支給については、所定の現金給与の代わりに支給するもの、その支給によって現金給与が減額されるものや労働協約によって支給が拘束されているものは賃金となります。
現物給与であっても、代金を徴収するものや福利厚生とみなされるものは原則として賃金とはなりません。
賃金に該当するもの
- 基本給
- 賞与
- 通勤手当
- 定期券・回数券
- 超過勤務手当・深夜手当等
- 扶養手当・家族手当・子供手当
- 技能手当
- 調整手当
- 地域手当
- 住宅手当
- 奨励手当
- 物価手当・生活補給金
- 休業手当
- 宿直・日直手当
- 雇用保険料・社会保険料
- 昇給差額
- 前払い退職金
賃金に該当しないもの
- 役員報酬
- 結婚祝金・慶弔見舞金
- 出張旅費
- 傷病手当金
- 解雇予告手当
- 福利厚生として事業主が負担するもの
賃金の定義
法律や統計などの目的によって、賃金の定義はさまざまです。
賃金にはさまざまな名称があり、労働基準法では「賃金」、健康保険法・厚生年金保険法では「報酬」、所得税法では「給与」などと呼ばれています。
労働基準法
労働基準法で「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
健康保険法・厚生年金保険法
健康保険法・厚生年金保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものすべてをいいます。
ただし、臨時に受けるものおよび3ヵ月を超える期間ごとに受けるものは含まれません。
所得税法
所得税法の「給与」とは、俸給、給料、賃金、歳費および賞与並びにこれらの性質を有するもののことをいいます。
賃金の形態
賃金の支払または計算単位の違いによる基準を賃金支払形態といいます。
労働時間を単位として計算する定額制と生産量などによって算出する出来高払い制があります。
定額制はさらに、1時間、1日、1ヵ月、1年等、賃金を支払う対象期間に対応して、時間給制、日給制、週給制、月給制、年俸制があります。
出来高払い制には、出来高給制、歩合給制、業績給制等の形態があります。
賃金支払の5原則
賃金の支払い方について、労働基準法では5つの原則を定めています。
賃金が確実に労働者の手に渡るようにするために、罰則付で厳格に規制されています。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月払いの原則
- 一定期日払いの原則
通貨払いの原則
賃金は現金で支払われなければなりません。
法令で定められているものや労働協約で定められたものは、労働者の同意を得て、現物支給や口座振込もできます。
賃金の口座振込については、必要な条件があります。
- 労働者の同意があって、労働者の指定する本人名義の口座であること
- 賃金の総額が所定の支給日に引き出せるようになっていること など
直接払いの原則
賃金は直接本人に支払われます。家族であっても、代理人などに支払うことはできません。
ただし、本人が病気療養中で家族が賃金を受け取るようなケースは、原則に反しないと解されています。
全額払いの原則
賃金は全額を支給しなければならず、一部を控除して支給することはできません。
ただし、雇用保険料と社会保険料の本人負担分や所得税、住民税は会社から支払うので、控除することができます。
また労働協約で定められたものは、労働者の同意を得て、一部控除して支払うことができます。
毎月払い・一定期日払いの原則
賃金は毎月1回以上、一定の期日を決めて支払われなければなりません。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与などは含まれません。
年俸制であっても、毎月1回以上、12回に分けて支払われます。
賃金支払の例外
賃金は原則として一定の期日に支払われますが、出産、病気、災害など非常時の費用に充てるために請求した場合には、支払期日前であっても、働いた分に対する賃金を使用者は支払わなければならない、とされています。
参考:厚生労働省ウェブサイト