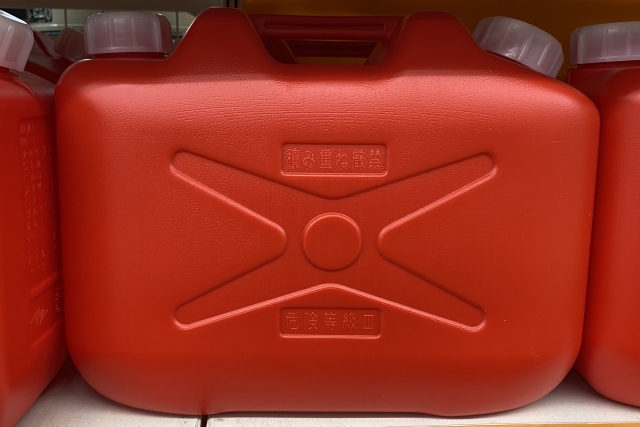危険物取扱者は、消防法で定められた危険物の取り扱いに必要な国家資格です。
危険物取扱者の資格は、取り扱いのできる危険物の種類により分かれています。
毎年多くの人が受験する人気資格の危険物取扱者についてご紹介します。
危険物取扱者の資格

危険物とは
危険物とは、ガソリン等の石油類、金属粉等の燃焼性の高い物品のことです。
消防法に定められた危険物は、6種類に分類されています。
第1類
酸化性固体。
それ自体は燃焼しませんが、可燃物を酸化して燃焼や爆発を起こす固体です。
- 塩素酸塩類
- 過塩素酸塩類
- 無機化過酸化物
- 亜塩素酸塩類
- 臭素酸塩類
- 過マンガン酸塩類 など
第2類
可燃性固体。
着火しやすい固体で、低温でも引火しやすい固体です。
- 硫化リン
- 赤リン
- 硫黄
- 鉄粉
- 金属粉
- マグネシウム など
第3類
自然発火性物質および禁水性物質。
空気や水と接触して発火したり、可燃性ガスを出す物質です。
- カリウム
- ナトリウム
- 黄りん
- アルカリ金属
- 金属の水素化合物
- カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 など
第4類
引火性液体。
引火しやすい液体です。
- 特殊引火物
- 第1石油類(ガソリン、ベンゼン、アセトンなど)
- アルコール類(メチルアルコール、エチルアルコールなど)
- 第2石油類(灯油、軽油など)
- 第3石油類(重油など)
- 第4石油類(潤滑油など)
- 動植物油類
第5類
自己反応性物質。
分子内に含まれる酸素で燃えたり爆発したりする物質です。
- 有機過酸化物
- 硫酸エステル類
- ニトロ化合物
- ニトロソ化合物
- アゾ化合物
- シアゾ化合物
- ヒドロキシルアミン など
第6類
酸化性液体。
それ自体は燃焼しませんが、可燃物を酸化して燃焼や爆発を引き起こす液体です。
- 過塩素酸
- 過酸化水素
- 硝酸 など
危険物取扱者について
一定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために危険物取扱者を必ず置かなければならないことになっています。
危険物取扱者の資格は、取り扱いのできる危険物により「甲種」「乙種」「丙種」の種類に分かれています。
甲種危険物取扱者
すべての危険物についての取り扱い作業とその保安監督、無資格者の取り扱いに対する立ち会いができる資格です。
乙種危険物取扱者
第1類から第6類の危険物のうち、資格を取得した危険物の取り扱い作業とその保管監督、無資格者の取り扱いに対する立ち会いができる資格です。
丙種危険物取扱者
ガソリン、灯油、軽油、重油など特定品目の危険物の取り扱いだけができる資格です。
保管監督や立ち会いはできません。
資格取得のメリット
危険物を取り扱う業種は幅広く、化学系メーカーや工場、印刷会社、薬品会社、ガソリンスタンドなどの転職・就職で有利になります。
資格手当や処遇アップも期待できます。
危険物取扱者免状の取得
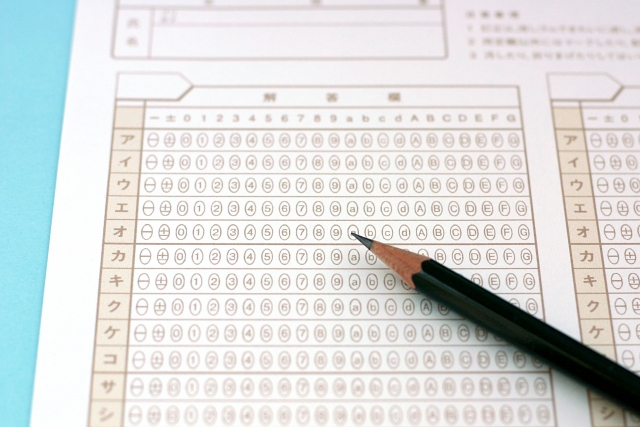
危険物取扱者試験
危険物取扱者になるには、試験に合格して免状を取得する必要があります。
取り扱いのできる危険物の分類ごとに「甲種」「乙種(1類~6類)」「丙種」の試験が行われます。
乙種4類は最も受験者数が多く全体の7割を占めています。
ガソリンや軽油など、活躍の場が広がる危険物を取り扱うことができるので、人気が高い資格となっています。
はじめて受験するのであれば、乙種4類から挑戦して、幅を広げていくことをおすすめします。
受験資格
乙種・丙種の試験については制限なく、誰でも受験することができます。
甲種の試験を受験する場合は、一定の資格が必要です。
次のいずれかに該当する人は甲種の受験資格があります。
- 学歴
大学、短期大学、高等専門学校等で化学に関する学科・課程を修めて卒業した人 - 単位
大学、短期大学、高等専門学校、大学院等で化学の科目を通算して15単位以上修得した人 - 実務経験
乙種危険物取扱者免状を有する人で、危険物製造所等における危険物取扱いの実務経験が2年以上の人 - 学位
修士、博士の学位所持者で、化学に関する事項を専攻した人(外国の同学位) - 資格者
次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状を有する人
(第1類まはは第6類、第2類または第4類、第3類、第5類)
試験日
各都道府県および試験区分により異なります。
- 前期:4月~9月
- 後期:10月~3月
試験地
各都道府県の指定された会場
試験方法
危険物取扱者試験は甲種、乙種、丙種いずれも筆記試験(マークシート)です。
合格基準は各科目とも60%以上の正解率です。
試験科目
| 資格 | 試験科目 | 問題数 |
| 甲種 | 危険物に関する法令 物理学及び化学 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 15問 10問 20問 |
| 乙種 | 危険物に関する法令 基礎的な物理学及び基礎的な化学 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 15問 10問 10問 |
| 丙種 | 危険物に関する法令 燃焼及び消火に関する基礎知識 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10問 5問 10問 |
試験科目の一部免除
乙種の試験において次に該当する人は試験科目の一部が免除されます。
- 乙種危険物取扱者免状を有する人
- 火薬類免状を有する人
- 乙種危険物取扱者免状を有し、かつ火薬類免状を所持する科目免除申請者
丙種の試験において次に該当する人は試験科目の一部が免除されます。
- 5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち基礎教育または専科教育の警防科を修了した人
合格率
- 甲種:30%程度
- 乙種:40%程度(乙種第4類は約30%)
- 丙種:50%程度
問い合わせ
一般財団法人 消防試験研究センター
危険物取扱者の資格勉強

資格取得の勉強法
危険物取扱者の資格を取得するためには、独学や資格・通信講座で勉強する方法があります。
基礎知識の有無や持っている資格など自分の状況やかけられる時間、費用に応じて、最適な方法を選ぶことが大切です。
危険物取扱者試験は、参考書などのテキストが比較的多く、独学でも合格を目指すことができます。
独学で合格を目指すのであれば、テキストを学習して、過去問題集を3回以上繰り返すことが基本になります。
独学に不安があったり、効率的に学習を進めたい人は、試験対策の通信講座などを上手に活用することをおすすめします。
資格の取得期間
人気の乙種第4類の合格率は30%程度です。
適当な勉強では受かりません。
働きながらの受験であれば、3ヵ月以上の準備期間を設けることをおすすめします。
効率的な勉強法
- 試験範囲全体に目を通す
- わからないところや苦手なところを確認する
- 問題集を繰り返し解く
学習のポイント
試験に合格するには、各科目60%以上の得点が必要となりますので、苦手科目を作らないようにすることが大切です。
まずは需要の多い乙種4種を取得して、試験科目の一部免除を利用して効率的に資格取得していくことをおすすめします。
乙種第4類おすすめテキスト&過去問
危険物取扱者の通信講座
はじめて受験する人や短期間で効率的に合格を目指す人にはお手頃価格の通信講座をおすすめします。

資格のステップアップ
危険物取扱者は、危険物の種類により乙種で1類から6類まであります。
人気の乙種4類から取得して、取り扱える危険物の種類を増やしてステップアップしていくことができます。
乙種4類合格後に実務経験を積むか、乙種で4種類以上の資格を取得すると、甲種の受験資格を得ることができます。
他に業務の幅を広げるのであれば、消防設備士の資格取得をおすすめします。
ビル資格
「危険物取扱乙種4類」と「2級ボイラー技士」、「第二種電気工事士」、「第三種冷凍機械」はビル資格の4点セットといわれています。
ダブル・トリプル取得していくことでキャリアアップに有利です。
消防設備士
消防設備士は消防用設備の工事・整備・点検を行うための国家資格です。
消防設備士試験も危険物取扱者試験と同じ試験機関が実施しています。
取り扱う設備が各類ごとに限定されていて、消火器を取り扱う乙種6類の受験者がもっとも多くなっています。
まとめ
危険物取扱者の資格は幅広い業界でニーズがあります。
求人では、危険物取扱者資格の保有者を優遇するという企業も多く、転職・就職では有利になります。
資格手当や昇格・昇進の期待ができ、スキルアップ、キャリアアップにも有効です。




【参考】
・一般財団法人 消防試験研究センター
・各試験実施機関ウェブサイト