消防設備士は、警報器やスプリンクラーなど消防用設備の工事・整備・点検を行うための国家資格です。
取り扱える消防用設備の種類によって、試験は甲種が特類と1~5類、乙種が1~7類に分けて実施されています。
建築物の着工件数の増加に伴い、消防設備士の需要も増えています。
ニーズが高まる消防設備士の資格の取り方と勉強法についてご紹介します。
消防設備士の資格

消防設備士とは
劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等または特殊消防用設備等の設置が法律により義務付けられています。
それらの工事、整備等を行うには消防設備士の資格が必要です。
取り扱う設備が各類ごとに限定されていて、免状に記載されている消防設備等の工事、整備、点検をすることができます。
甲種消防設備士
甲種消防設備士は、消防用設備等または特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができます。
乙種消防設備士
乙種消防設備士は、消防用設備等の整備、点検を行うことができます。
免状の種類
【甲種】
- 特類:特殊消防用設備等
【甲種または乙種】
- 第1類
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 - 第2類
泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 - 第3類
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 - 第4類
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 - 第5類
金属製避難はしご、救助袋、緩降機
【乙種】
- 第6類:消火器
- 第7類:漏電火災警報器
消防設備士の資格を取るには
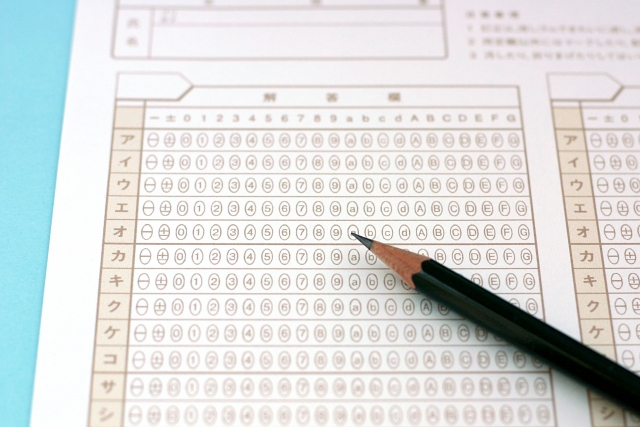
消防設備士試験
消防設備士の資格を取るには、消防設備士試験に合格して、免状の交付を受ける必要があります。
消防設備士試験には、甲種と乙種があり、各類ごとに取り扱う設備が限定されていますので、類ごとに免状が必要になります。
受験資格
- 甲種特類
甲種1~3類のうち1つと、甲種4類と甲種5類の3つの免状の交付を受けていること - 甲種特類以外
・大学、短大、高専、高校または中等教育学校で機械、電気、工業化学、土木または建築に関する学科・課程を修めた卒業者
・資格者(消防設備士、電気工事士、電気主任技術者、技術士等)
・消防用設備等工事の実務経験者 など - 乙種
制限なし
※詳細は、指定試験機関「一般財団法人 消防試験研究センター」のウェブサイトをご確認ください。
試験日
各都道府県、受験区分により異なります。
試験地
各都道府県
試験方法
- 筆記試験:マークシート(四肢択一式)
- 実技試験:写真・イラスト・図面などによる記述式
試験内容
- 甲種
・工事設備対象設備等の構造、機能、工事、設備
・火災及び防火
・消防関係法令
・基礎的知識
・消防用設備等の構造、機能、工事、整備 - 乙種
・消防関係法令
・基礎的知識
・構造、機能、整備
試験の一部免除
消防設備士、電気工事士、電気主任技術者、技術士等の資格者は、申請により試験科目の一部が免除されます。
合格率
- 甲種:30%程度
- 乙種:40%程度
問い合わせ
一般財団法人 消防試験研究センター
転職・就職情報
消防設備士を必要とする施設は法律で義務づけられているため、建築や工事、整備等が増えれば、消防設備士の資格者の需要も増加します。
試験の実施状況
消防設備士試験の受験者は年々増加し、毎年多くの人が受験しています。
甲種では4類、乙種では6類の受験者が多くなっています。
甲種
| 区分 | 受験者 (人) | 合格者 (人) | 合格率 (%) |
| 特類 | 913 | 266 | 29.1 |
| 1類 | 8,872 | 1,887 | 21.3 |
| 2類 | 3,136 | 930 | 29.7 |
| 3類 | 3,096 | 765 | 24.7 |
| 4類 | 14,029 | 4,441 | 31.7 |
| 5類 | 2,891 | 980 | 33.9 |
| 甲種計 | 32,937 | 9,269 | 28.1 |
一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況(令和5年度)」より
乙種
| 区分 | 受験者 (人) | 合格者 (人) | 合格率 (%) |
| 1類 | 1,540 | 423 | 27.5 |
| 2類 | 504 | 133 | 26.4 |
| 3類 | 795 | 189 | 23.8 |
| 4類 | 6,011 | 2,115 | 35.2 |
| 5類 | 878 | 306 | 34.9 |
| 6類 | 18,719 | 7,192 | 38.4 |
| 7類 | 4,108 | 2,488 | 60.6 |
| 乙種計 | 32,555 | 12,846 | 39.5 |
一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況(令和5年度)」より
消防設備士の資格勉強

資格取得の勉強法
消防設備士の資格を取得するには、独学や資格・通信講座で勉強する方法があります。
基礎知識の有無や持っている資格など学習レベルやかけられる時間、費用など自分の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。
テキストや問題集が市販されていますので、独学でも合格を目指すことができます。
独学に不安があったり、効率的に学習を進めたい人は受験対策の通信講座を上手に活用することをおすすめします。
資格の取得期間
受験者数の多い乙種6類の合格率は40%程度です。
甲種で受験者数が多い4類は30%程度の合格率です。
働きながら勉強するのであれば、2~3ヵ月程度の準備期間はあった方がよいでしょう。
消防設備士乙種6類のおすすめテキスト&問題集
消防設備士第4類のおすすめテキスト&問題集
消防設備士の通信講座
企業の利用も多い技術講座専門のJTEXでは、技術系通信講座を数多く取り扱っています。
消防設備士受験講座では、試験に合格できる実力を身につけられるカリキュラムを提供しています。
資格のステップアップ
消防設備士は、取り扱える設備により乙種で1類から7類まであります。
人気の乙種6類から取得して、取り扱える設備を広げてステップアップしていくことができます。
乙種の合格後に実務経験を積むと、甲種の受験資格を得ることができます。
甲種の資格を取得すると、整備・点検だけでなく、工事ができるようになります。
さらに業務の幅を広げるのであれば、危険物取扱者の資格を取得することをおすすめします。
危険物取扱者試験
危険物取扱者は、危険物を製造、貯蔵、取り扱いをする場所で必要とされる資格です。
危険物とは燃焼性の高いガソリン等の物品のことで、化学工場、ガソリンスタンドなどの施設には、危険物取扱者を必ず置かなければならないことになっています。
危険物取扱者試験も消防設備士試験と同じ試験機関が実施しています。
危険物取扱者試験は、危険物の種類によって各類ごとに実施されます。
需要が多いのは乙種4類で、多くの人が乙種4類から受験しています。
まとめ
消防設備士は需要が多く、受験者も増えている資格です。
人気の乙種6類から取得をはじめて、取り扱える設備を増やしていくことで、活躍の場を広げることができます。
参考:一般財団法人消防試験研究センター







