公害防止管理者は、特定の工場に配置が義務付けられている環境技術者の資格です。
一定規模以上の生産設備のある工場では資格者の配置と届け出が義務付けられています。
自然環境を守る公害防止管理者の資格の取り方と勉強法についてご紹介します。
公害防止管理者の資格

公害防止管理者
公害防止管理者は、公害発生施設または公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。
公害防止管理者は、公害発生施設の区分ごとに選任しなければなりません。
公害防止管理者の資格を取得するには、国家試験に合格する方法と認定講習を受講する方法があります。
国家試験は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音または振動の防止等に関して必要な知識および技能を所持しているかどうかを筆記試験によって判定します。
試験の区分は公害防止管理者について12区分、公害防止主任管理者について1区分の計13区分に分かれています。
試験の合格者には、それぞれの区分に応じて合格証書が付与されます。
公害防止管理者の種類
- 大気関係第1種公害防止管理者
- 大気関係第2種公害防止管理者
- 大気関係第3種公害防止管理者
- 大気関係第4種公害防止管理者
- 水質関係第1種公害防止管理者
- 水質関係第2種公害防止管理者
- 水質関係第3種公害防止管理者
- 水質関係第4種公害防止管理者
- 騒音・振動関係公害防止管理者
- 特定粉じん関係公害防止管理者
- 一般粉じん関係公害防止管理者
- ダイオキシン類関係公害防止管理者
- 公害防止主任管理者
特定工場とは
公害防止管理者の選任が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。
対象となる事業内容が
- 製造業(物品の加工業を含む)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
のいずれかに属すること
次の施設を設置している工場
- ばい煙発生施設
- 特定粉じん発生施設
- 一般粉じん発生施設
- 汚水等排出施設
- 騒音発生施設
- 振動発生施設
- ダイオキシン類発生施設
公害防止管理者の資格を取るには

公害防止管理者の国家試験
公害防止管理者の資格を取得するには、国家試験を受験して、一定の合格基準を満たす方法があります。
科目別合格制度が取られており、合格した科目は3年まで申請により科目免除されます。
合格証書が資格を証明する書類となります。
定期的な更新制度はなく、永年資格です。
受験資格
制限なし
試験日
年1回(10月)
試験地
全国の主要都市(札幌、仙台、東京、愛知、大阪、広島、高松、福岡、那覇)
※会場は年によって異なります。
試験科目
- 公害総論
- 大気概論
- 大気特論
- ばいじん・粉じん特論
- 大気有害物質特論
- 大規模大気特論
- 水質概論
- 汚水処理特論
- 水質有害物質特論
- 大規模水質特論
- 騒音・振動概論
- 騒音・振動特論
- ばいじん・一般粉じん特論
- ダイオキシン類概論
- ダイオキシン類特論
- 大気・水質概論
- 大気関係技術特論
- 水質関係技術特論
科目別合格制度
- 科目合格に基づく科目免除
受験した試験区分を構成する一部の科目に科目合格すると、同じ試験区分を受験する場合に限り、最初に合格した年を含め3年までは、受験者の申請により、合格科目の受験を免除できます。 - 区分合格に基づく科目免除
ある試験区分に合格し資格を取得すると、後年、別の試験区分を受験する際、受験者の申請により、共通科目を免除できます。
合格率
25%程度
問い合わせ
一般社団法人 産業環境管理協会
公害防止管理者の資格認定講習
公害防止管理者資格認定講習を受講し、修了試験を受験し、修了基準を満たすと公害防止管理者の資格を取得することができます。
定期的な更新制度はなく、永年資格です。
受講資格
講習区分ごとに定められている技術資格、または学歴に応じた実務経験者
※詳細は産業環境管理協会ウェブサイトからダウンロードできる受講案内書で確認することができます。
実施日
12月~3月の時期
実施場所
全国主要都市(札幌、仙台、東京、愛知、大阪、広島、高松、福岡)
聴講免除制度
国家試験または認定講習で公害防止管理者の資格を取得した人は、新たに別の講習区分を受講する場合、既に取得した区分と共通する科目の講義の聴講が免除されます。
免除されるのは聴講だけで、修了試験はすべての科目範囲を受ける必要があります。
資格取得の条件
- 受講資格を満たしている
- 規定の講習時間を聴講する
- 修了試験を受講し、修了基準を満たす
問い合わせ
一般社団法人 産業環境管理協会
公害防止管理者の資格勉強
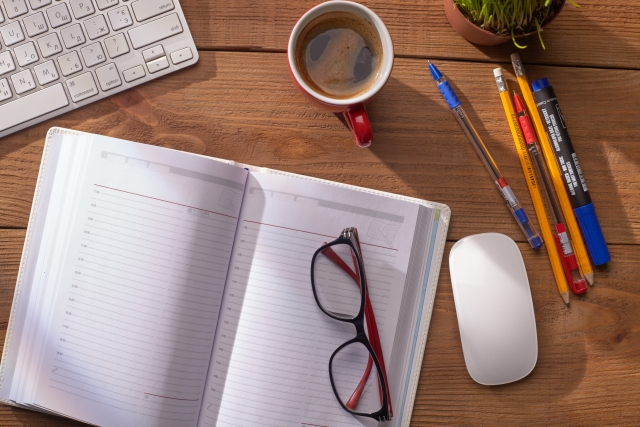
資格取得の勉強法
公害防止管理者の資格を取得するには、独学や資格・通信講座で勉強する方法があります。
基礎知識や受講資格の有無、かけられる時間・費用など自分の状況に合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。
公害防止管理者の公式テキストや過去問題集が市販されていますので、独学でも国家試験の合格を目指すことができます。
独学に不安のある人や認定講習の受講資格がある人は、講習を受講+修了試験の合格で資格を取得することができます。
公害防止管理者認定講習のテキスト
公害防止管理者試験の問題集
まとめ
公害防止管理者は法律上配置と届け出が義務付けられている資格です。
認定講習には受講資格がありますが、国家試験は誰でも受けることができます。
資格者は環境技術者として製造業で高く評価されます。
簡単な試験ではありませんが、資格を取得することはキャリアでの評価を高めることに役立ちます。


【参考】
・経済産業省ウェブサイト
・一般社団法人産業環境管理協会



