介護福祉士は介護職で唯一の国家資格です。
介護業界におけるキャリアパスの仕組みが整備され、介護福祉士の資格取得の重要性が高まっています。
介護福祉士になるには、国家試験に合格する必要があります。(養成施設を2026年度までに卒業する人を除く)
介護福祉士の筆記試験科目と対策についてご紹介します。
介護福祉士の資格

介護福祉士とは
介護福祉士は、身体や精神に障がいのある人や日常生活を送すことが難しい人の心身の状況に応じた介護を行い、介護に関する指導を行います。
社会福祉士、精神保健福祉士と並ぶ福祉系の3大国家資格です。
キャリアの活かし方
- 介護老人保健施設
- 特別養護老人ホーム
- デイケアセンター
- 病院などの医療施設 など
介護福祉士になるには
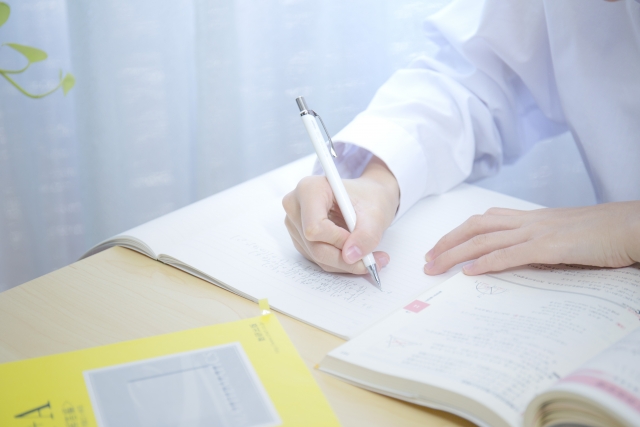
介護福祉士国家試験
介護福祉士は、国家試験に合格するか養成施設を修了して、所定の登録を受けることににより資格を取得できます。
介護福祉士の国家試験では、筆記試験と実技試験が実施され、介護福祉士として必要な知識および技能が問われます。
実技試験は筆記試験合格者のみが対象ですが、福祉系高校ルートと経済連携協定(EPA)ルートの受験者以外は実技試験が免除されています。
受験資格
- 3年以上介護等の業務に従事した実務者研修の修了者
- 介護福祉士養成施設を卒業した人
- 福祉系高等学校を卒業した人 など
試験日
- 筆記試験:1月
- 実技試験:3月
試験地
- 筆記試験:全国の35試験地
- 実技試験:東京、大阪
筆記試験
- 人間と社会
・人間の尊厳と自立
・人間関係とコミュニケーション
・社会の理解 - 介護
・介護の基本
・コミュニケーション技術
・生活支援技術
・介護過程 - こころとからだのしくみ
・発達と老化の理解
・認知症の理解
・障害の理解
・こころとからだのしくみ - 医療的ケア
・医療的ケア - 総合問題
・総合問題
実技試験
介護等に関する専門技能(筆記合格者のみ)
介護福祉士の筆記試験科目
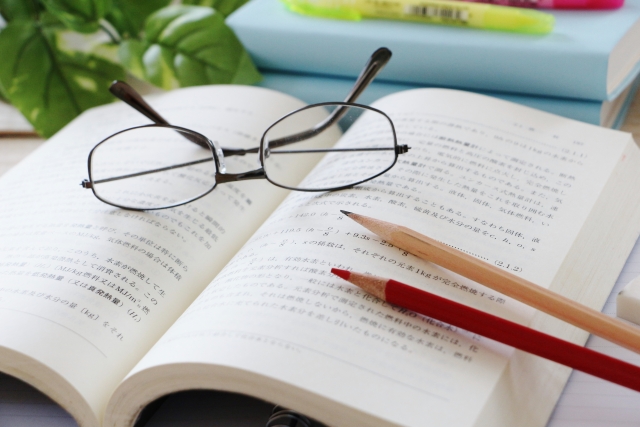
人間と社会
人間と社会の領域からは法制度や基礎知識が中心に出題されます。
人間の尊厳と自立
人間の尊厳と自立からの試験出題数は2問程度で、学習する内容は他の科目でも触れられる内容です。
- 人間の尊厳と自立
- 介護における尊厳の保持・自立支援
人間関係とコミュニケーション
人間関係とコミュニケーションからの試験出題数は2問程度で、難易度はそれほど高くなく、学習しやすい科目といえます。
- 人間関係の形成
- コミュニケーションの基礎
社会の理解
この科目の試験出題数は12問程度と多く、難易度も高くなっています。
- 生活と福祉
- 社会保障制度
- 介護保険制度
- 障害者自立支援制度
- 介護実践に関連する諸制度
介護
介護の領域からは介護の実践的な内容が中心に出題されます。
介護の基本
介護の基本からの試験出題数は10問程度で、他の科目と関連する内容が多く含まれていて、難易度はそれほど高くありません。
- 介護福祉士を取り巻く状況
- 介護福祉士の役割と機能を支えるしくみ
- 尊厳を支える介護
- 自立に向けた介護
- 介護を必要とする人の理解
- 介護サービス
- 介護実践における連携
- 介護従事者の倫理
- 介護における安全の確保とリスクマネジメント
- 介護従事者の安全
コミュニケーション技術
コミュニケーション技術からの試験出題数は8問程度で、難易度はそれほど高くありませんので、得点しやすい科目といえます。
- 介護におけるコミュニケーションの基本
- 介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション
- 介護におけるチームのコミュニケーション
生活支援技術
生活支援技術からの試験出題数は20~26問程度で、難易度はそれほど高くありませんが、学習量は多い科目です。
- 生活支援
- 自立に向けた居住環境の整備
- 自立に向けた身じたくの介護
- 自立に向けた移動の介護
- 自立に向けた食事の介護
- 自立に向けた入浴・清潔保持の介護
- 自立に向けた排泄の介護
- 自立に向けた家事の介護
- 自立に向けた睡眠の介護
- 終末期の介護
介護過程
介護過程からの試験出題数は8問程度で、難易度はそれほど高くありませんので、得点しやすい科目といえます。
- 介護過程の意義
- 介護過程の展開
- 介護過程の実践的展開
- 介護過程とチームアプローチ
こころとからだのしくみ
こころとからだのしくみの領域からは、医学・心理学的な内容が中心に出題されます。
発達と老化の理解
発達と老化の理解からの試験出題数は8問程度ですが、内容が深く、学習量は多い科目です。
- 人間の成長と発達の基礎的理解
- 老年期の発達と成熟
- 老化に伴うこころとからだの変化と日常生活
- 高齢者と健康
認知症の理解
認知症の理解からの試験出題数は10問程度で、認知症についてしっかり理解していないと対応できない科目です。
- 認知症を取り巻く状況
- 医学的側面から見た認知症の基礎
- 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活
- 連携と協働
- 家族への支援
障害の理解
障害の理解からの試験出題数は10問程度で、学習量はそれほど多くありませんが、重要な科目です。
- 障害の基礎的理解
- 障害の医学的側面の基礎的知識
- 連携と協働、家族への支援
こころとからだのしくみ
こころとからだのしくみからの試験出題数は12問程度ですが、学習量は多い科目です。
- こころのしくみの理解
- からだのしくみの理解
- 身じたくに関連したこころとからだのしくみ
- 移動に関連したこころとからだのしくみ
- 食事に関連したこころとからだのしくみ
- 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみ
- 排泄に関連したこころとからだのしくみ
- 睡眠に関連したこころとからだのしくみ
- 死にゆく人のこころとからだのしくみ
医療的ケア
医療的ケアの領域からは医療的な内容が中心に出題されます。
医療的ケア
医療的ケアは2016年度から新たに追加された科目で、試験出題数は5問程度です。
- 医療的ケア実施の基礎
- 喀痰吸引(基礎的知識・実施手順)
- 経管栄養(基礎的知識・実施手順)
総合問題
総合問題はすべての領域から事例形式で出題されます。
総合問題
総合問題からの試験出題数は12問で、学習内容の応用的な科目です。
介護福祉士の筆記試験対策
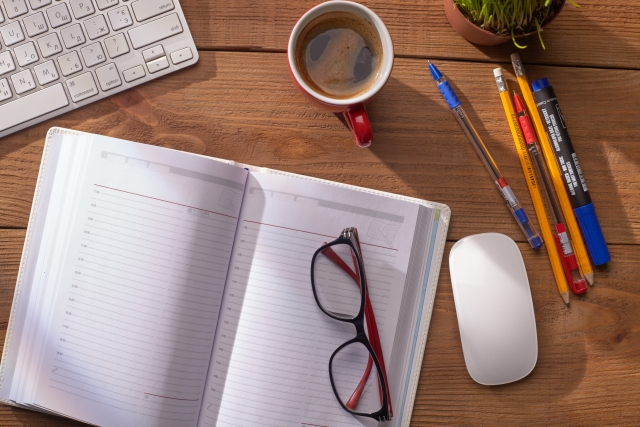
試験対策の勉強法
介護福祉士の筆記試験対策としては、独学や資格・通信講座で勉強する方法があります。
介護福祉士の筆記試験は出題範囲が広く、暗記が必要な内容も多く含まれています。
国家試験に合格するためには、出題傾向を押さえて国家試験のための対策をする必要があります。
学習の状況やかけられる時間、費用などに合わせて最適な方法を選ぶことが大切になります。
資格の取得期間
テキストや過去問題集が市販されていますので、独学でも筆記試験の合格を目指すことができます。
独学に不安があったり、働きながら効率よく学習を進めたい人は、資格・通信講座を上手に活用することをおすすめします。
講座は1ヵ月~半年程度のカリキュラムが多くなっています。
学習のポイント
過去問題集を中心に勉強を進めることがポイントになります。
過去問題集を繰り返し解き、試験問題に慣れることが大切です。
間違えた問題など疑問点はテキストで解決して、理解を深めるようにします。
介護福祉士のおすすめテキスト
介護福祉士の過去問題集
介護福祉士国家試験の対策講座
介護福祉士の受験には、実務者研修が必須となっています。
まだ受験資格のない人は、まず実務者研修を受講して受験資格を得ることをおすすめします。
国家試験の受験を予定している人は、受験対策講座の受講がおすすめです。
まとめ
介護福祉士は働きながら目指す人が多い試験ですので、仕事と勉強を両立させることが重要になります。
限られた時間で効率的に合格を目指すには、過去問を繰り返し解くことがポイントになるといえるでしょう。



【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・公益財団法人社会福祉振興・試験センター



