退職するときに、退職日をその月の最終日(月末)とその前日(月末前日)のどちらにするか?
どちらが得か損かなど、聞いたことがあるかもしれません。
実は、その1日の差で、保険料の支払いに違いが出ます。
あとから後悔しないために、自分の退職(転職)プランに合うのは、どちらなのか事前に知っておきましょう。
月末退職と月末前日退職についてご紹介します。
月末退職と月末前日退職

退職とは
退職とは、企業と従業員が雇用関係(労働契約)を終了して、従業員が企業を辞めることです。
雇用関係が終了するには、いくつかのパターンがありますが、自己都合退職では、従業員からの意思表示により成立します。
就業規則などの社内ルールに従って、従業員が退職する時期を決めることができるといえます。
雇用関係の終了
- 自己都合退職
- 契約期間の満了
- 合意解約
- 解雇
- 会社の解散等
社会保険の負担
社会保険とは、「厚生年金」「健康保険」「介護保険」のことです。
広い意味では、労働保険の「雇用保険」「労災保険」とあわせて、公的保険を意味して使われます。
適用事業所はこれらの公的保険に加入しなければなりません。
労災保険は全額会社負担ですが、その他の保険料は従業員にも負担分があり、従業員が負担する保険料は毎月の給与から控除されています。
社会保険の保険料
厚生年金、健康保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて計算され、日割りという考え方はありません。
介護保険料の支払いは40歳からです。
労働保険の保険料
雇用保険の保険料は、実際に支払われた給与に保険料率をかけて計算されますので、日割りであれば日割りした給与をベースに計算すればよいことになります。
労災保険の保険料は全額会社負担ですので、保険料の給与控除はありません。
保険料の支払い
厚生年金や健康保険の社会保険料は「資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月まで徴収される」と定められています。
3月31日付で退職する人は、翌日の4月1日に被保険者資格を失いますので、前月である3月分まで徴収(給与控除)となります。
3月30日付で退職する人は、3月31日に資格を失いますので、前月である2月分まで徴収となります。
1日の違いで1ヵ月分の保険料の支払いに差が出ます。
厚生年金の手続き
3月30日付の退職であれば、3月分の厚生年金の保険料は徴収されませんが、国民年金には加入して保険料を支払う必要があります。
厚生年金より国民年金の保険料の方が安いかもしれませんので、しばらく会社に勤務しない人にとっては、負担が軽くなるといえます。
しかし、将来、受け取る年金額は減ることになります。
4月1日から次の会社への入社が決まっているような場合、3月の1ヵ月分だけ国民年金に加入することは、手続きが煩雑になり、ほとんどメリットはないといえるでしょう。
健康保険の手続き
3月30日付で退職して、4月1日に次の会社へ入社するような場合、3月分の保険料は支払わずに、3月30日までは今の会社の健康保険が使えます。
退職後、本来は国民健康保険に加入しなければなりませんが、3月31日の1日はケガや病気をしないように、あるいは病院へ行くのを我慢して、4月1日からは次の会社の健康保険に入ることで、1ヵ月分の健康保険料は徴収されません。
当然ですが、保険に加入していない31日に病院にかかるような事態になれば、全額自己負担となりますので、あまりおすすめはできません。
退職日と最終出社日
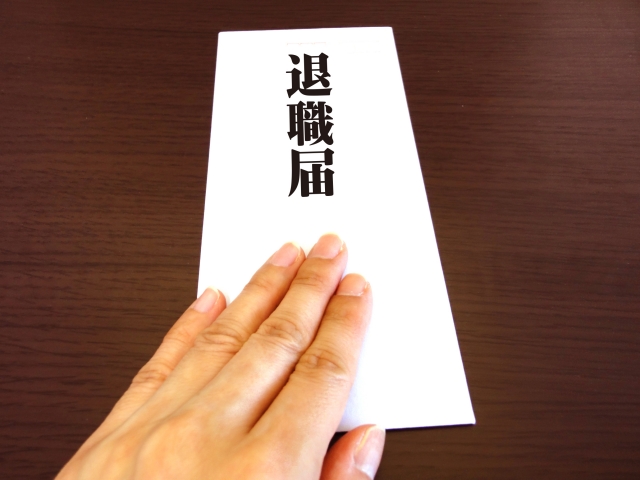
退職日の決め方
退職日は雇用契約を終了する日で、最終出社日は最後に会社に行く日です。
退職日と最終出社日は、同じ日でなければならないと思っていませんか?
退職日と最終出社日は、同じ日ではなくても大丈夫です。
月末の最終日が日曜日に当たる場合、土日は会社が休みだからという理由で、退職日をその月の最終金曜日などにする必要はありません。
月末退職にしないことで、1ヵ月分の保険料は徴収されませんが、自分でしなければならない手続きが出てきますし、その手続きをしないことで、年金に空白期間ができてしまうことになります。
月末退職と月末前日退職のどちらがよいかは個人の状況やそのあとの予定によって変わってきます。
再就職・転職する場合
退職後、すぐに次の勤め先で働くことが決まっているような場合には、次の勤務との空白ができない日を退職日に決めましょう。
退職日が休日となり出社しない日であっても、退職日として問題ありません。
その場合、退職日と最終出社日が別の日になるということです。
退職金制度がある場合
退職金は任意の制度ですので、退職するときに誰でももらえるというものではありません。
退職金制度がある場合、支給額の計算に勤続月数を使うことが多くあります。
勤続月数のカウントやポイントの付与がいつなのかによって、退職日が退職金の支給額に影響することがあります。
例えば、勤続月数のカウントやポイント付与がその月の16日以降の在籍者とされている場合、15日付で退職すると退職金の支給額を計算する勤続月数が1ヵ月分少なくなるということになります。
最終出社日の決め方
それぞれの事情により、退職日と最終出社日が同じ日にならないことは少なくありません。
退職する前に残っている年次有給休暇を消化したいという人も多いでしょう。
年次有給休暇を取得する人の最終出社日は、業務の引き継ぎ状況と年次有給休暇の取得期間を考慮して決めます。
業務の繁忙期などを無視した申し出はトラブルのもとですので、問題のなさそうなタイミングを事前に考えておくことが大切です。
年次有給休暇のルール
年次有給休暇は従業員が希望する日に自由に取得できる休暇です。
しかし、繁忙期などで正常な業務の運営に支障が出る場合などは、会社から従業員に対して、取得時季の変更を働きかけることができます。(会社の時季変更権)
引き継ぎが終わっていない状況で、まとめて休暇を取得するということは、認められない場合もあります。
就業規則などに規定されている社内のルールは確認しておきましょう。
退職するときに返却するもの
退職すると資格を失う保険証や社員証、会社から貸与されていた制服やノートパソコンなどはすべて退職日までに返却しなければなりません。
最終出社日が退職日より前であれば、最終出社日までに返却すればよいですが、保険証など退職日まで持っていた方がよいものもあります。
社内のルールを確認して、トラブルにならないように退職日と最終出社日を決めましょう。
職場の人は退職日と最終出社日が違うことをわかっていても、退職手続きをする人事や総務の担当者が把握していない場合、退職手続きを完了できない可能性があるからです。
会社へ返却が必要なものを確実に返すのはもちろん、会社から受け取る必要があるものも確認しておきましょう。
まとめ
月末退職と月末前日退職のどちらが得か損かは、それぞれの人の置かれた状況や今後の予定、扶養する家族の有無などでも変わってきます。
両方のメリット・デメリットを比較して、自分にとってよい方を退職日に決めればよいのです。
翌月初日から次の会社での勤務が決まっているのであれば、迷わず月末退職を選ぶことをおすすめします。



【参考】
・日本年金機構ウェブサイト
・全国健康保険協会ウェブサイト



