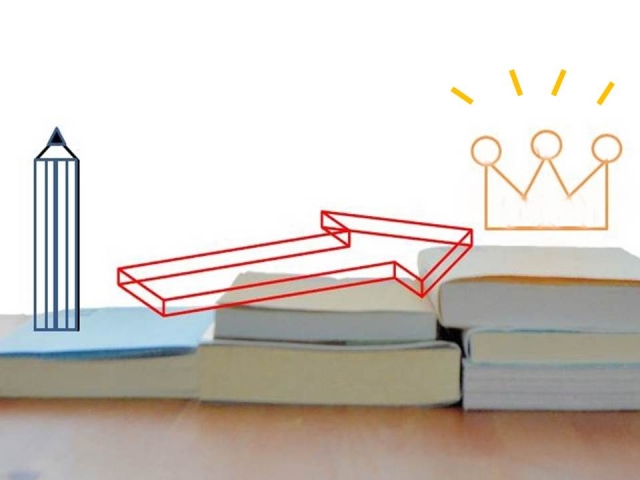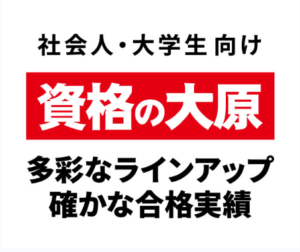社会保険労務士は労務管理の国家資格として人気があります。
労働・社会保険に関する幅広い知識が求められますので、社会保険労務士試験に短期合格するためには、効率的に勉強を進めることがポイントとなります。
過去問を中心に独学で合格を目指すこともできますが、短期合格は難しいかもしれません。
膨大な試験範囲から、重要事項を絞って、効率的に勉強を進めるためには通信講座を上手に活用することをおすすめします。
社会保険労務士(社労士)のオンライン・通信講座

社会保険労務士の通信講座はたくさんあり、それぞれのコースには特徴があります。
働きながら効率的に短期合格を目指すためにおすすめの社労士通信講座をご紹介します。
社労士通信講座おすすめランキング
合格者の声
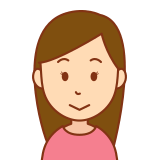
社労士試験に必要なことが濃縮された講義を視聴することで、短時間で、社労士試験の勉強ができるところが魅力だと思います。(資格の大原/社労士24+直前対策)
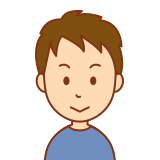
朝出勤する前や、移動時間は講義動画で学習したりしました。空いた時間ではeラーニングを活用して小問題を解くというというような形で学習していました。
法律初学者の私でも一発で合格することができました。
(フォーサイト/試験対策バリューセット)
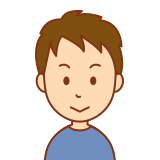
Web講座で講師が選べることです。講師との相性が必ずあると思いますし、各人の勉強のスタイルに合う講師がいいと思いますので、大変良かったと思います。受講形態もWebでは速度をあげて聴くことができるので、時間の節約にも資することができました。」
(LEC東京リーガルマインド/上級コース受講)
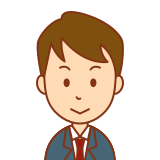
音声のみの配信や動画配信の倍速モードなど、働きながら時間が取れない私とっては非常に効率的に勉強することができたと感じております。
(アガルートアカデミー/社労士試験合格カリキュラム)
引用:各スクールウェブサイトより
通信講座を選ぶポイント
通信講座のコースやカリキュラムには、それぞれ特徴があります。
自分の希望に合う講座を見つけて上手に活用することが大切です。
講座の確認
- 受講料などかかる費用は確認しましたか?
- 受講後に目指せる資格は希望と合っていますか?
- テキストやコンテンツなどの内容は気に入りましたか?
- 希望するサポートやフォローを受けられますか?
社会保険労務士の国家試験

社労士の試験概要
社会保険労務士試験は合格率が10%未満の難関試験ですが、さまざまな受験回数の受験者がいますので、合格率がそのまま試験の難易度につながるわけではありません。
試験対策をしっかりすれば合格できる資格といえます。
受験資格
- 一定の学歴があること
・大学、短期大学の卒業
・大学における修得単位数
・専門学校の卒業
・厚生労働大臣が認めた学校の卒業 など - 学歴を問わず通算3年以上の実務経験があること
- 他の国家試験等に合格していること
・社労士試験以外の国家試験
・司法試験予備試験等
・行政書士試験
いずれかを満たしていることが必要です。
試験日
年1回( 8月)
試験方法
- 選択式:各問ごとに空欄があり、与えられた選択肢の中から選んで空欄を埋める
- 択一式:5肢択一
試験科目
- 労働基準法及び労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労務管理その他の労働に関する一般常識
- 社会保険に関する一般常識
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
合格率
8%程度
問い合わせ
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験センター
社労士の試験科目
社会保険労務士試験は8科目で10分野から出題されます。
基本はもちろんですが、改正点は出題される可能性が高いので、新聞などでも最新情報をおさえておく必要があります。
労働基準法
労働基準法は労働条件の最低基準などを定めた法律です。
総則、労働契約、労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇、就業規則からの出題率が高く、判例からも出題されます。
労働安全衛生法
労働安全衛生法は労働基準法と一緒に出題され、例年数問の出題です。
安全衛生管理体制についての出題が中心で、労働者の就業にあたっての措置、健康の保持増進などもポイントです。
労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法は一般的に労災保険法と呼ばれる法律です。
保険給付に関する出題が多く、改正点をしっかりチェックしておく必要があります。
雇用保険法
雇用保険法は雇用全体の安定を図ることを目的とする法律です。
雇用保険法からは失業給付等は継続して出題されています。
給付金や助成金、手続きや届出に関してもよく出題されます。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
労働保険徴収法は労働保険の保険料の額及び納付の手続きについて定めた法律です。
一般的には徴収法と呼ばれます。労働保険料の納付の手続きは、具体的に保険料額の計算や納付金額についても理解する必要があります。
健康保険法
健康保険は被保険者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡又は分娩に関して保険給付を行う社会保険制度です。
健康保険法からは全般的に出題されますので、十分な理解が必要です。
厚生年金保険法
厚生年金保険法は原則として報酬比例の年金を支給する制度です。
厚生年金保険法からは保険給付からの出題が多く、改正や経過措置などを理解しておく必要があります。
国民年金法
国民年金は公的年金制度共通の基礎年金です。
国民年金法からは被保険者、給付、保険料から万遍なく出題されます。
労務管理その他の労働に関する一般常識
労働管理その他の労働に関する一般常識については、最新の労働白書の内容を理解しておくことが必要です。
社会保険に関する一般常識
社会保険に関する一般常識については、社会保険全般の幅広い知識が必要になります。厚生白書などに目を通しておくことが必要です。
社会保険労務士の勉強法
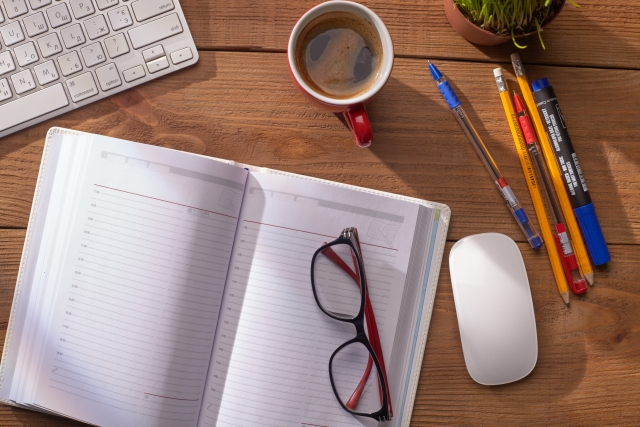
社労士の試験準備
社会保険労務士試験に合格するには、ある程度まとまった勉強時間を確保する必要があります。
試験問題は法改正などの影響を受けますので、長期計画ではなく、短期計画で臨むことをおすすめします。
試験対策には、独学や通学・通信講座で勉強する方法がありますが、講座の合格実績などよりも、自分に合った勉強方法を見つけ、組み合わせるなど効果的に取り組むことが大切です。
資格の取得期間
社会人であれば仕事の後や休日に勉強時間を確保する必要があります。
人事・労務関係の仕事や法律の学習経験がある人、離職中など時間を確保できる人は1年から1年半、それ以外の人は2年程度を目標として準備期間を取るとよいでしょう。
社労士講座の受講費用
スクールによって受講費用はさまざまです。
通信講座では大体50,000円~200,000円程度、通学・スクールの場合では120,000円~250,000円程度になります。
高額の講座でも、コースや講師陣が充実していたり、資格取得後のサポートがしっかりしているなどメリットも多くあります。
自分の状況やかけられる時間、費用に合わせて、希望する学習スタイルを選ぶことが大切です。
社労士の試験対策
社会保険労務士試験に短期間で合格するためには、自分に合った方法で勉強することが一番重要です。
効率的に最短で合格するために共通して必要なポイントは3つです。
基本テキストをマスターする
いろいろなテキストに手を出すのではなく、講座の教材や自分がわかりやすいと思ったテキストを重点的に学習することをおすすめします。
過去問題集を解く
過去問を10回以上反復して、正解率が8割を超えるようになれば、合格レベルに近くなっていると考えられます。
模擬試験を受験する
本試験前に模擬試験が実施されますので、1回は受験しておきましょう。
最新の試験傾向を知ることができますので、過去問と同様にしっかりおさえておくことをおすすめします。
まとめ
社会保険労務士試験に合格するために、満点を目指す必要はありません。
試験に出る範囲の基本を押さえて、過去問を繰り返し、合格レベルに達することが重要です。
膨大な試験範囲からそのポイントを絞るのは、独学では難しく、講座を受講する1番のメリットは短期合格のための効率的な学習法を入手できることだといえます。


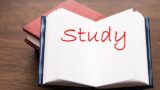


【参考】
・社会保険労務士試験オフィシャルサイト
・各スクールウェブサイト