保育士の資格は、保育士養成校を卒業しなくても、保育士試験に合格すれば、取得することができます。
保育士試験は、各都道府県で毎年1回行われています。
平成27年度から年2回目の試験として、地域限定保育士試験を実施していますが、平成28年度より、地域限定保育士試験に加えて、通常の保育士試験についても、一部の地域で年2回目の試験が行われています。
社会人からでも資格取得を目指しやすい環境が整えられています。
保育士試験の実施状況(2022年度)
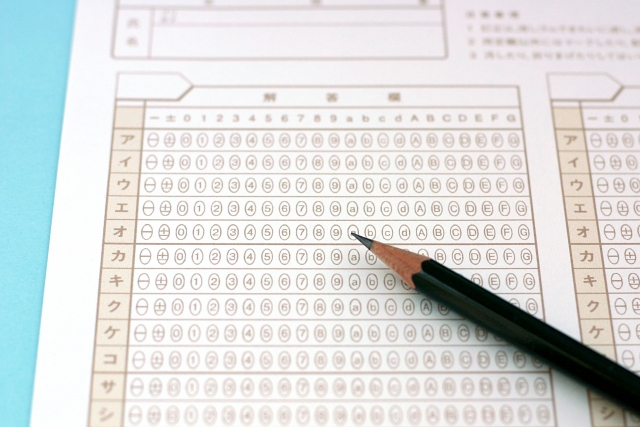
保育士試験の受験資格
保育士試験で保育士になるには、試験に合格して、保育所に採用される必要があります。
受験資格
- 4年制大学を卒業した人
- 4年制大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した人
- 短期大学や専修(専門)学校を卒業した人
- 高等学校卒業の場合は、児童福祉施設で2年以上児童の保護に従事した人
- 中学校卒業の場合は、児童福祉施設で5年以上児童の保護に従事した人
- 幼稚園教諭免許の取得者 など
保育士の筆記試験と実技試験
保育士試験では筆記試験と実技試験が行われます。
筆記試験は全部で8科目、1科目ずつ別々に合格が判定されます。
1度に全科目に合格できなくても、合格した科目は3年間有効です。
実技試験は筆記試験に合格した人のみが受験できます。
保育に関する表現技術の分野から2分野を選択して受験します。
試験日
- 筆記試験:4月、10月
- 実技試験:7月、12月
試験方法
- 筆記試験:マークシート形式
- 実技試験:実演による採点
試験科目
- 筆記試験
・保育原理
・教育原理
・社会的養護
・子ども家庭福祉
・社会福祉
・保育の心理学
・子どもの保健
・子どもの食と栄養
・保育実習理論 - 実技試験
・音楽に関する技術
・造形に関する技術
・言語に関する技術
地域限定保育士試験
地域限定保育士試験の合格者は、3年間は合格した都道府県内のみの通用となりますが、登録後3年経過すれば、全国で働ける保育士となります。
問い合わせ
一般社団法人 全国保育士養成協議会
保育士試験の合格率
保育士試験を受けて資格を取得する人は年々増加しています。
合格率はここ数年20%程度と低めに推移してきましたが、2022年度は30%程度に上昇しています。
都道府県別の結果
| 都道府県 | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 合格率 (%) |
| 北海道 | 2,393 | 723 | 30.2 |
| 青森県 | 315 | 77 | 24.4 |
| 岩手県 | 388 | 95 | 24.5 |
| 宮城県 | 1,086 | 290 | 22.5 |
| 秋田県 | 256 | 76 | 26.7 |
| 山形県 | 517 | 143 | 27.7 |
| 福島県 | 579 | 165 | 28.5 |
| 茨城県 | 1,429 | 393 | 27.5 |
| 栃木県 | 957 | 256 | 26.8 |
| 群馬県 | 638 | 190 | 29.8 |
| 埼玉県 | 4,272 | 1,329 | 31.1 |
| 千葉県 | 4,572 | 1,435 | 31.4 |
| 東京都 | 14,600 | 4,500 | 30.8 |
| 神奈川県 | 10,200 | 2,552 | 25.0 |
| 新潟県 | 870 | 275 | 31.6 |
| 富山県 | 296 | 93 | 31.4 |
| 石川県 | 428 | 110 | 25.7 |
| 福井県 | 229 | 63 | 27.5 |
| 山梨県 | 376 | 108 | 28.7 |
| 長野県 | 825 | 303 | 36.7 |
| 岐阜県 | 757 | 240 | 31.7 |
| 静岡県 | 1,723 | 551 | 32.0 |
| 愛知県 | 4,396 | 1,524 | 34.7 |
| 三重県 | 652 | 209 | 32.1 |
| 滋賀県 | 903 | 313 | 34.7 |
| 京都府 | 1,659 | 534 | 32.2 |
| 大阪府 | 6,273 | 1,995 | 31.8 |
| 兵庫県 | 3,149 | 1,066 | 33.9 |
| 奈良県 | 840 | 277 | 33.0 |
| 和歌山県 | 332 | 93 | 28.0 |
| 鳥取県 | 256 | 70 | 27.3 |
| 島根県 | 188 | 66 | 35.1 |
| 岡山県 | 961 | 289 | 30.1 |
| 広島県 | 1,364 | 414 | 30.4 |
| 山口県 | 484 | 148 | 30.6 |
| 徳島県 | 375 | 109 | 29.1 |
| 香川県 | 392 | 124 | 31.6 |
| 愛媛県 | 545 | 168 | 30.8 |
| 高知県 | 267 | 67 | 25.1 |
| 福岡県 | 2,574 | 741 | 28.8 |
| 佐賀県 | 520 | 145 | 27.9 |
| 長崎県 | 490 | 145 | 29.6 |
| 熊本県 | 741 | 181 | 24.4 |
| 大分県 | 461 | 142 | 30.8 |
| 宮崎県 | 554 | 133 | 24.0 |
| 鹿児島県 | 1,112 | 312 | 28.1 |
| 沖縄県 | 2,184 | 526 | 24.1 |
| 合計 | 79,378 | 23,758 | 29.9 |
(こども家庭庁「保育士試験の実施状況(令和4年度)」より)
保育所や児童養護施設などで働くためには、各児童福祉施設の採用試験を受験することになります。
公立の施設の場合には、公務員試験を受験する必要があります。
保育士試験の受験者
保育士試験の受験者には、社会人経験者や働きながら目指す人が多くいます。
合格科目が3年間有効ですので、3年間かけて合格を目指す人が多くなっています。
6回以上受験する人も10%いますので、それぞれの状況に合わせたペースで受験していることがわかります。
保育士試験合格者の受験回数
- 2回目(32.9%)
- 3回目(22.1%)
- 初めて(15.0%)
- 4回目(13.0%)
- 6回以上(10.1%)
- 5回目(6.6%)
(全国保育士養成協議会「保育士試験合格者の就職状況等に関する調査研究」より)
保育士試験の支援
厚生労働省では、保育士資格を取得しやすくするための新たな取り組みを実施しています。
保育士試験の年2回実施の推進
- 年1回以上行うこととされている保育士試験について、年2回実施されるよう推進
- 地域限定保育士試験の合格者には、3年程度当該都道府県内のみで通用する「地域限定保育士」資格を付与し、3年経過後は地域を限定せずに働くことを可能とする
保育士試験の学習費用支援
保育士試験合格後、保育所等に保育士として勤務することが内定した人に対して、保育士試験の受験のためにかかった学習費用の一部を補助する取り組みを行っています。(教育訓練給付などとの併用は不可)
保育士試験に合格するには

保育士の試験対策
保育士試験に合格するためには、独学よりも試験に対応したカリキュラムで効率的に学習することをおすすめします。
知識の習得とともに、保育や子どもに関するニュースや法律を意識しておくことも大切です。
保育士資格の通信講座
保育士試験の筆記8科目は最長3年間で取得できればよく、保育士試験に対応した通信講座では、受講期間の無料延長などのサポートがあります。
教育訓練給付制度対象講座であれば、社会人経験のある20代・第二新卒はお得に受講できます。

保育士試験の特徴
保育士試験に合格して保育士を目指すため人は、保育士試験のメリット・デメリットを確認しておきましょう。
メリット・デメリット
まとめ
保育士試験の合格率は20~30%ですが、筆記試験は科目別に最長3年間で合格すればよく、合格ラインは6割程度ですので、未経験からでもチャレンジしやすい試験といえます。
働きながら自分のペースで資格取得を目指すことができ、最短であれば6ヵ月程度で合格することもできます。
認可外保育施設とされていた一部の事業が地域型保育事業として認可されるようになり、保育士のニーズはますます増えることが見込まれます。



【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・一般社団法人 全国保育士養成協議会ウェブサイト



