若手で転職を考える人には、年功序列の企業より成果主義の企業の方が
「若手でも活躍できそう」
「中途採用も不利にならなそう」
「お給料もいいのでは?」
という印象があるのではないでしょうか。
年功序列制を見直す企業が増える一方で、年功序列を評価している企業もあります。
成果主義と年功序列の企業、転職するならどちらがいいのか?
それぞれの制度についてメリット・デメリットをご紹介します。
成果主義と年功序列の人事制度

人事制度とは
人事制度とは、企業の従業員を活かすための基準や運営の仕組みのことです。
人事制度は、企業の経営戦略に合わせて構築されます。
組織の目的や方向性、風土によって、採用する制度も違ってきます。
人事制度には、賃金・給与制度や人事評価制度、目標管理制度などがあります。
人事制度は、一度構築したら、それで終わりというわけではなく、さまざまな状況に応じて見直しがされます。
この数十年で日本の企業を取り巻く環境は大きく変化し、人事制度では、年功主義から成果主義へと大きな流れがありました。
さらに成果主義から役割・職務を基準とする人事制度の導入が進んでいます。
経営環境の変化
- グローバル化
- IT化
- 低成長化
- 人件費の高騰化
社会環境の変化
- 少子高齢化
- 女性活躍の推進
- 長時間労働の削減
- 雇用形態の多様化
- ワークライフバランスの重視
企業の課題
- 働き方改革
- テレワーク
- 育児・介護休業
- 定年延長・再雇用
成果主義のメリット・デメリット

成果主義とは
成果主義とは、職務の成果や業績など企業への貢献度を基準として、給与や処遇を決定することです。
年功序列の不公平感を排除して、社員のモチベーションアップ、組織の活性化を目的として導入が進みました。
成果主義の人事制度では曖昧さを排除して、事前に成果を特定することが前提となっています。
外資系企業では一般的でしたが、日本企業でも導入が進みました。
成果主義のメリット・デメリット
成果主義で失敗する例
- 結果だけを重視し、成果以外には客観性がない評価をして、従業員の不満が高まる
- 短期的な目標・結果を追求し、長期的視点を持たなくなる
- 個人主義が助長し、部署間や組織内でのつながりが希薄化し、チームワークが軽視される
- 後進の育成より自らの職務とスキルアップを優先して、人材が育たなくなる
- リスクが高い新規ビジネスなどへの挑戦意欲が低下し、革新的な商品・サービスが生まれにくくなる
成果主義がうまくいく例
- 成果を上げるために従業員を育成することを重視する
- 結果主義ではなく、仕事に携わる貢献度を評価する
- 事前に成果を特定し、合意する
- 成果につながるプロセス・過程を把握する
- 成果につながる行動を把握する
成果主義の目的は社員のモチベーションアップによる組織の活性化です。
年功序列のメリット・デメリット
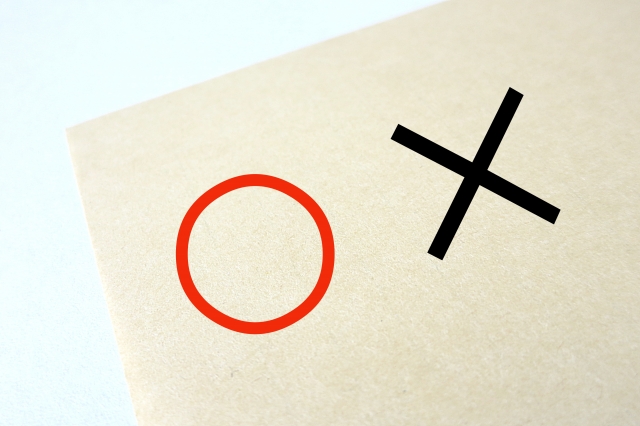
年功序列制とは
年功序列制とは、年齢や勤続年数などに応じて、給与や処遇がほぼ自動的に上昇する制度のことです。
年齢や勤続年数が同じであれば、昇給や昇格・昇進にほとんど差がつきません。
終身雇用を前提とした正社員の長期勤務、安定期など条件がそろった状況で有効に機能してきました。
年功序列のメリット・デメリット
年功序列の課題
年功序列制では従業員が長期勤務することで能力を蓄積し、貢献度が高まることを前提としています。
しかし、経済情勢の変化、雇用形態の多様化など実情に当てはまらないことが多くなってきています。
ベースアップや定期昇給は年功序列制の賃金制度を支えてきましたが、見直しをする企業が増えています。
やる気や実力を重視する企業や即戦力の中途採用に積極的な企業では、脱・年功序列の流れがさらに加速すると考えられます。
年功序列制は日本企業の終身雇用を支えてきた処遇制度です。
まとめ
成果主義と年功序列、どちらにもメリット・デメリットがありますし、運用はそれぞれの企業の方針で変わってきます。
成果主義の運用には問題点も指摘され、結果のみを重視する成果主義は見直されてるようになっています。
これからの成果主義は年功序列の不公平感を解消し、若くても職務や業績への貢献度が高い従業員を評価することがポイントになります。
やる気と実力のある従業員を適切に処遇する企業の就職・転職人気は高くなります。
公平で納得性の高い人事制度は応募する企業を決めるうえで、重要な要素のひとつになっています。



【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・経済産業省ウェブサイト



